こんにちは。
いつもブブログをご覧頂きありがとうございます。
当記事では、「高齢者の人工栄養の話し合い」についてまとめています。
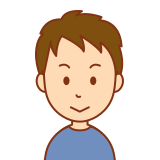
高齢者の介護をする家族にとっては、人工栄養についての話し合いは非常に重要事件であり、難しい問題です。
特に人工栄養の話し合いは、医療の教科書通りの進め方で解決できる問題ではないのです。
病院でも、何度も何度も話し合いを重ねてきても、それぞれの家庭によって解釈は違ってきます。
当たり前な言い回しですが、「同じ人はいない」と言うことです。
非常に難しく専門的なテーマであり、お手本通りの考え方がリスクになる事もあります。
つまり「皆さんこうしている」とか「今後の方針は決めました」とかにはならないと言うことです。
当記事では、胃ろうや中心静脈栄養といった人工栄養の歴史と、その変遷、実際の問題について考える機会になれば幸いです。
目次
高齢者の人工栄養の話し合い

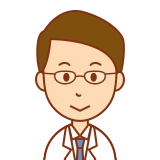
はじめに、人工栄養の歴史を簡単に紹介したいと思います。
- 何事も歴史から学ぶことは多いものです。
- 経験や歴史から学ぶことが重要です。
あまり人工栄養の歴史について書いているブログなどはないので貴重だと思います。
歴史的に最も古いのは1744年に経鼻胃管をした記録が残っています。
経鼻胃管とは、鼻から60センチ前後のチューブを胃までいれる事です。
オランダの内科医であるHerman Boerhaaveという方が、解毒剤を投与する目的で柔らかい金属製のチュー ブを胃の中に入れたのが経鼻胃管の始まりとされています。
その後徐々にゴム製のチューブが使用されるようになり、当初から薬物や栄養を投与する経路や、術後の処置として用いられてきました。
そのついでと言ったらおまけのようですが、外科的な胃ろう造設術が誕生しています。
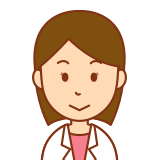
この手術を世界で初めて成功させたのが1875年イギリスの外科医であるSydney Jones医師といわれています。
その後も手技としての改良が進みましたが、最も画期的な転機は1980年で、アメリカの小児科医であるMicahel Gauderer医師が、中枢神経障害児に対して施行した内視鏡を使った胃瘻造設術です。
この革命的な発明によって、胃ろうはより身近で利用しやすいツールへとなりました。
その歴史はわずか数百年であり、まだまだ新しい技術といえます。
中心静脈栄養(total parenteral nutrition : TPN)について

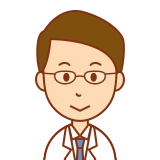
中心静脈栄養(total parenteral nutrition : TPN)の始まりは、1969年で比較的最近のことです。
アメリカの外科医である Stanley Dudrick医師が、腸回転異常症による消化吸収の新生児に応用したのが最初でした。
1970年代に多くの新生児や小児患者に対するTPN報告がなされ、さらには成人でもTPNが普及していきました。
一方、ここ数年胃ろうによる経管栄養を受けている患者が少しずつ減っています。
その原因は、日本や欧米を中心に広まっている「胃ろうに対するバッシング」が影響しているのかもしれません。
「認知症患者に経管栄養をしない」という提言も発表されています。
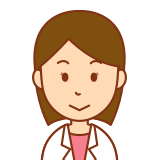
また日本でも、テレビ報道や国会議員の発言などを通して、胃ろうが好ましくないケアであるような世論が目立つようになり、胃瘻に関する手術の報酬も下げられました。
その後の日本国内での胃ろう手術件数は明らかに減少傾向となています。
大分本末転倒な歴史を辿っているなか、それぞれのエビデンスを確認してみましょう。
人工栄養(胃ろう・経鼻胃管・中心静脈栄養)のエビデンス

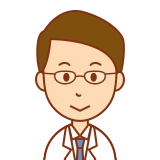
人工栄養のエビデンスでまず重要なのは「誰に介入したか」です。
たとえば脳卒中など、急性期で治療可能性のある疾患では治療のための「時間稼ぎ」として人工栄養を使用することがあります。
これは嚥下機能障害のある認知症終末期の患者に行う人工栄養とは区別する必要があります。
誰に介入したエビデンスかを考えずに得られたエビデンスを適用することは御法度です。
経管栄養のエビデンス
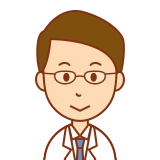
認知症の高齢者に対する経管栄養(胃ろう・経鼻胃管)のエビデンスを調べると、2009年のCochrane reviewと言う文献に行き当たります。
少なくとも経管栄養を使用した集団が生存率を改善したというエビデンスはないというものです。
つまり認知症の終末期の方に積極的な栄養の摂取はあまり効果がないと言うことが書いてあります。
この研究の対象は、アメリカの高齢施設に入所している認知症の高齢者の約3万6000人を調べたものです。
平均80歳で嚥下障害の発症から1年以内に経管栄養が開始されています。
この研究結果でも、胃ろうは非胃ろうと比較して1年後死亡率に有意差がなかったと報告されています。
中心静脈栄養のエビデンス
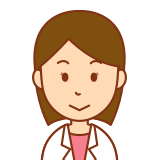
中心静脈栄養については、人工栄養(artificial nutrition)の適応はありますが、消化管が使えないなどの経管栄養が禁忌に該当する場合のみに検討することと推奨されています。
特に認知症の高齢者における中心静脈栄養という領域は残念ながらほとんどエビデンスが存在しません。
一方、現実的な問題として経口摂取ができない高齢者において、中心静脈栄養が選択される頻度はかなり多いです。
その場合に中心静脈栄養管理が可能な医療機関や、介護施設への転院が行われている現状があります。
昨今の胃ろう造設減少の結果として、このような状況に拍車がかかっているとしたら、高齢者医療としては残念なことです。
さらに中心静脈栄養管理に関連する医療費が、経管栄養のよりも高額であることも影響しているのかもしれません。
実際どう考えどう行動するか?

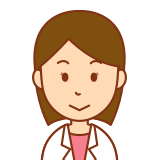
認知症の高齢者に対する人工栄養のエビデンスは、実はあまり確固としたものがないことがわかりました。
予後についても、1年生存率が増えると考える場合と、1年死亡率も高いと考える場合とで印象は異なるかもしれません。
結局その問題にどのような関心や期待をもっているかによって、エビデンスをみたときの印象は大きく異なります。
どこまでいっても完璧なエビデンスなどといったものは存在しません。
人工栄養を開始するかどうかの選択において、エビデンスが提供するのはあくまで情報であり、その情報をどう活かすかは受け手の問題です。
人工栄養を巡る意思決定の際には、人工栄養のエビデンス以外にも重要な点は多くあります。
- 人工栄養が本当に必要か
- 十分な可逆的要因を検討できたか
といった必要性の検討です。
これは本当に終末期か?という点とも類似する問いです。
また、意思決定の際に本人不在になりやすい点にも留意する必要があります。
認知症などにより、本人の意思決定が難しい場合には意思決定の主体が家族になりがちです。
そして、家族は人工栄養を希望する傾向が強いが、あくまで重要なのは本人の人生にとって現在得られているエビデンスを基に、患者および家族と十分にコミュニケーションを取り意思決定していく必要があります。
人工栄養の効果を高いと思うか低いと思うかは、情報提供側および受け取り側双方の問題が大きく、受け入れられない、受け入れたくないと思うこと自体は十分理解可能な思考過程です。
まとめ
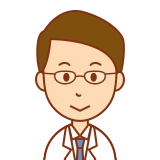
高齢者の経口摂取困難時における人工栄養のエビデンスについて深掘りしてみました。
エビデンスはあくまで意思決定の材料であり、この材料を基にそれぞれの患者・家族支援者と繰り返し話し合い、患者意向を反映した意思決定ができるかが重要です。
そしてどんな意思決定がなされたとしても、その決定をできる限りサポートできる世の中であると良いと思います。


